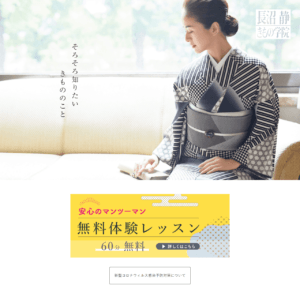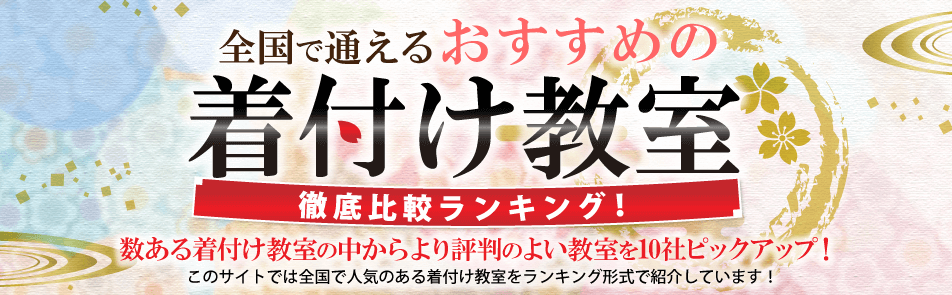
着物の柄の意味を知って着物選びの参考にしよう!

着物の柄には、それぞれに異なる意味が込められています。そして「着物を着るからには、柄に込められた意味を知ってから選びたい」と考える人は一定数いるでしょう。そこで今回は、植物文様、動物文様、そのほかの柄それぞれに与えられた意味を詳しく解説していきます。本記事が、着物選びの参考になれば幸いです。
植物文様に込められた意味
着物に描かれる植物文様は、写実的なものと抽象的なものに大別されます。
写実的な文様は季節感を反映し、着用する季節が限定される一方、抽象的な文様は通年で使用可能です。振袖は未婚女性の第一礼装であり、とくに季節を問わず着用できます。
桜
桜は日本の国花として親しまれ、新たなスタートを象徴する縁起のよい柄です。
五穀豊穣や繁栄を意味し、成人式やフォーマルな場に適しています。ほかの草花と組み合わせることで通年着用可能です。
松竹梅
松竹梅は吉祥文様の代表格で、松は長寿、竹は成長、梅は生命力を象徴します。
この組み合わせは厳寒に耐える美しさを表し、お祝いの席にふさわしい柄です。橘は日本固有の植物で、繁栄や長寿、子孫繁栄を意味し、婚礼衣装にも多用されます。
唐草文様
唐草文様は生命力や子孫繁栄を象徴し、蔦の途切れない形状が縁起を担います。
日本では松や梅、菊と組み合わせて描かれることが多いです。
牡丹
牡丹は「富貴の花」として高貴さや美しさ、不老長寿を象徴し、とくに唐獅子と組み合わされると強い吉祥の意味をもちます。
紅葉は長寿や世渡りの上手さを意味し、ほかの文様と組み合わせることで通年で着用可能です。
青もみじ
青もみじ柄は初夏、紅葉柄は秋に適しています。
しかし、散った葉のデザインも広く使用されています。
葡萄
葡萄(ブドウ)は豊穣や子孫繁栄を象徴する文様です。
秋に実る特性から秋の柄として扱われることが多いですが、ほかの文様と組み合わせれば季節を問わず使用可能です。
動物文様に込められた意味
振袖に描かれる動物の文様には、それぞれ深い意味や願いが込められています。
これらのモチーフは縁起物として古くから親しまれ、成人式や結婚式などのフォーマルな場にふさわしい柄として選ばれます。
蝶
蝶は、蛹から成虫へと変化する過程から「不死」や「立身出世」を象徴しています。
とくに二匹の蝶が向き合う「向い蝶」は伝統的な柄で、優美さを感じさせる吉祥文様です。礼装だけでなく、普段着物にも用いられることがあります。
兎
兎は繁殖力の高さから子孫繁栄や豊穣を象徴し、福を呼び寄せる長い耳や飛躍を願う姿が縁起物として描かれます。
月の使いとされ、ツキ(幸運)を招く意味も込められています。
鶴
鶴は長寿や夫婦円満の象徴で「千年の鶴」と呼ばれるようにその生命力を称えられています。
結婚式や成人式などお祝いの場にふさわしく、松竹梅と組み合わされることも多いです。デザインは気品あふれるものから幻想的なものまで幅広く、振袖に華やかさを加えます。
鳳凰
鳳凰(ほうおう)は架空の生き物ですが、気高さや豪奢さを象徴し、平和や祝福の意味が込められた吉祥文様です。
祝い事やフォーマルな場でよく使われる代表的な柄です。
龍
龍も鳳凰と同様、架空の生き物でありながら神の化身として信仰されてきました。
水神として出世や飛躍を象徴し、厳格で力強い印象を与える柄です。男児用の着物に用いられることが多い一方で、振袖に描かれることもあります。こうした柄には日本の伝統的な美意識と祈りが反映されており、着物のもつ特別な意味を際立たせます。
そのほかの柄と込められている意味
着物の柄には、植物や動物だけでなく、縁起のよいとされる多彩な文様があります。
これらの文様は祝儀や祝い事の品物にも広く用いられ、人生の節目を祝う場にふさわしい意味をもっています。
手毬
手毬(てまり)は、丸い形状から「円満な家庭」や「どのような困難も丸く収まり、弾むような幸せが続く」という願いが込められています。
また、手毬に使われる糸には「良縁を結ぶ」意味もあり、華やかで縁起のよい文様です。
御所車
御所車(ごしょぐるま)は、貴族が使用していた牛車をモチーフとした高貴な柄で、桜など四季の草花や吉祥文様と組み合わされることが多いです。
その優雅さと上品さから成人式の振袖にもよく用いられます。
青海波
青海波(せいがいは)は、重なる波を幾何学的に表現した文様で、無限に広がる波を象徴しています。
「穏やかで幸せな日々が永く続くように」という願いが込められ、四季の草花などと組み合わされて多様なデザインが展開されています。
熨斗
熨斗(のし)は薄切りの乾燥アワビを起源とし、祝い事に欠かせない吉祥文様です。
複数の熨斗が束ねられた「束ね熨斗文」は、さらに縁起がよいとされています。
雲取り
雲取り(くもどり)は、雲の形を表した文様で、運気上昇や輪廻転生を象徴します。
風に流れる雲の自由さを表現し「悠々自適な人生を願う」という意味も込められています。道長取りは、藤原道長が好んだとされる曲線を基にした柄で、和紙をちぎって貼り合わせたような独特のデザインが特徴です。
貝桶
貝桶(かいおけ)は、平安時代の遊び「貝合わせ」で使われた入れ物をモチーフにしており、一対の貝が「永遠の契り」や「夫婦円満」を象徴します。
貝桶と草花などの文様が組み合わされることで、華やかで美しい柄が生まれます。
まとめ
着物の柄には、それぞれがもつ意味や願いが込められており、選ぶ際の大切なポイントとなります。植物文様では、桜が新たな始まりを象徴し、松竹梅は長寿や成長、生命力を表すなど、四季や生命を讃える意味が込められています。動物文様では、鶴が長寿と夫婦円満、鳳凰が平和と祝福、蝶が変化や成長を象徴し、それぞれ華やかで縁起のよいモチーフとして振袖を彩るでしょう。さらに、手毬や青海波、熨斗といったそのほかの文様も、家庭円満や幸せの永続といった願いが込められ、フォーマルな場にふさわしい選択肢です。着物の柄を理解し、その背景にある意味を知ることで、より特別な一着を選ぶ手助けとなるでしょう。