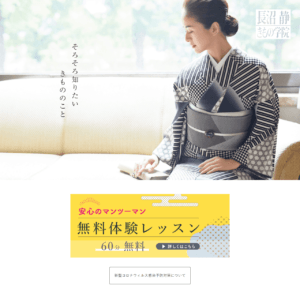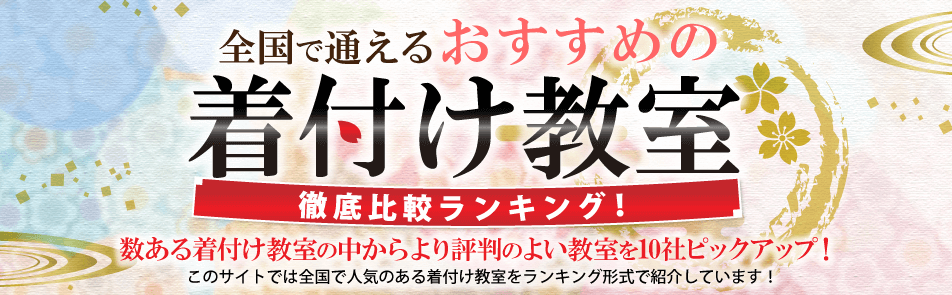
季節ごとの適切な着物の選び方を解説
 着物及び小物選びにおいては、季節を考慮することも大切です。季節に合わせた適切な着物選びは、健康を守るうえで欠かせません。本記事では、季節ごとの着物の種類や柄をまとめて紹介します。本記事の内容を参考にして、ぜひ季節ごとにマッチした素敵な着物姿を実現させてください。
着物及び小物選びにおいては、季節を考慮することも大切です。季節に合わせた適切な着物選びは、健康を守るうえで欠かせません。本記事では、季節ごとの着物の種類や柄をまとめて紹介します。本記事の内容を参考にして、ぜひ季節ごとにマッチした素敵な着物姿を実現させてください。
着物は季節ごとに種類がある
着物は一年を通して着用できますが、季節によって適した種類を選ぶのが一般的です。これは洋服が季節に応じて素材や形を変えるのと同様で、着物も主に3種類に分けられ、それぞれに適した着用時期があります。
袷(あわせ)
まず、10月から5月にかけて着用されるのが袷です。裏地を付けて仕立てられた厚みのある着物で、成人式や入学式、卒業式、七五三など、格式ある行事の時期と重なるため、最も着用機会の多い種類といえます。
袷の時期でも、気温に合わせて長襦袢(ながじゅばん)を調整することで快適に過ごすことが可能です。特に冬場には、ウール素材の袷を選ぶことで防寒性も高まります。また、黒留袖などの礼装は年間を通して袷仕立てが基本であり、季節を問わず着用しても失礼には当たりません。
単衣(ひとえ)
次に、6月と9月に着用されるのが単衣(ひとえ)です。裏地のない軽やかな仕立てで、初夏や初秋の気候に適しています。衣替えの時期にあたりますが、近年は気温の上昇により、5月下旬頃から単衣を取り入れる人も増えています。
単衣は通気性がよく、透け感のある長襦袢と組み合わせることで見た目にも涼しげです。6月には夏らしい明るい色や軽い素材を、9月には秋を感じさせる色味を取り入れるなど、季節の先取りを意識した装いが好まれます。
薄物(うすもの)
最後に、7月と8月の盛夏に着用されるのが薄物(うすもの)です。「絽(ろ)」「紗(しゃ)」「麻(あさ)」などの透け感のある素材で仕立てられ、見た目にも涼やかさを演出します。
薄物の着物は長襦袢が透けて見えるほど軽やかで、夏ならではの風情を楽しむことができます。ただし、薄物はあくまで盛夏専用であり、9月に入ると気温が高くても着用を控えるのが一般的です。
帯・長襦袢・小物選びのポイント
着物の装いでは、季節に応じて帯や長襦袢、小物を変えることが大切とされています。帯には大きく「袋帯(ふくろおび)」と「名古屋帯(なごやおび)」の2種類があり、前者は裏地付きで格式が高く、後者は一枚仕立てで軽やかさが特徴です。季節によって着物が変わるように、帯も季節感を意識して選ぶことで、より洗練された印象になります。
まず、袷(あわせ)や単衣(ひとえ)着物に合わせる帯は、フォーマルな場面では重厚感のある袋帯が基本です。単衣にはつづれ織を合わせることもあります。一方、カジュアルな装いには名古屋帯や博多帯(はかたおび)などを用いるとよく、帯の柄や色で季節を先取りするのがおしゃれです。
たとえば、6月の単衣の時期には、透け感のある「絽(ろ)」の帯を取り入れると、初夏らしい涼しさを演出できます。続いて、盛夏の7月・8月に着用する薄物(うすもの)には、「絽」「紗(しゃ)」「麻(あさ)」といった透け感のある帯を合わせます。フォーマルな場では袋帯を、普段使いには名古屋帯や、夏らしい紗献上帯(しゃけんじょうおび)などがいいでしょう。
薄物に合わせる帯の柄には、アジサイや波模様など季節を感じさせる意匠が多く、見た目にも涼やかな印象を与えます。また、長襦袢(ながじゅばん)や小物の選び方も重要です。袷着物には袖無双仕立ての長襦袢を合わせ、季節が進むと袖も単衣にする場合があります。
半衿は白の塩瀬(しおぜ)、帯揚げや帯締めは正絹が一般的です。単衣着物には単衣または絽の夏襦袢を合わせ、半衿や帯揚げも絽にして軽やかさを出します。薄物には絽の夏襦袢を用い、帯揚げや帯締めも涼感ある素材にするのがポイントです。
季節ごとにおすすめの着物の柄
着物には四季折々の自然や風物詩をモチーフにした多彩な柄があり、季節ごとに異なる美しさを楽しむことができます。春夏秋冬それぞれにふさわしい柄や色を取り入れることで、季節感を演出しながら上品な装いを楽しむのが日本の伝統的な着こなし方です。
春
春の着物には、桜や藤、牡丹、杜若(かきつばた)、菖蒲(しょうぶ)といった花柄がよく使われ、春の訪れや生命の息吹を感じさせます。また、蝶や鶯(うぐいす)など春の生き物をモチーフにした柄も人気で、優雅で穏やかな雰囲気を醸し出します。色合いは淡いピンク、薄紫、若草色などの柔らかなトーンが多く、全体に明るく華やかな印象を与えられるでしょう。
夏
夏の着物では、朝顔、あじさい、なでしこ、竹、柳、笹などの植物に加え、流水や波などの水の動きを表現した文様が定番です。こうした柄は、見た目にも涼しげで清涼感を感じさせるため、単衣(ひとえ)や薄物の着物に特によく映えます。配色は藍色や白、水色などの寒色系が中心で、爽やかで清潔感のある印象を与えます。
秋
秋には、紅葉、すすき、銀杏、萩、桔梗、菊、ぶどう、ざくろなど、秋の実りや草花を描いた柄が多く用いられます。落ち葉や花が風に舞う様子を表現した「吹き寄せ模様」も人気で、秋の情緒を繊細に表します。色合いは深緑、朱赤、からし色など、温かみのある落ち着いたトーンが好まれ、大人っぽい雰囲気を引き立てることでしょう。
冬
冬の着物には、雪輪、椿、水仙、松、梅、竹、橘、南天などがあしらわれ、寒さの中でも凛とした美しさを演出します。特に松竹梅や鶴亀といった縁起の良い文様は、フォーマルな場にもふさわしく、お正月や祝いの席に最適です。色調は深い藍や黒、えんじ色などのシックな色が中心で、上品さと温かみを感じさせる冬らしい装いとなります。
まとめ
着物は一年を通して楽しめる日本の伝統衣装ですが、季節ごとに素材・柄・色を変えることで、その魅力はさらに深まります。春は桜や藤などの花柄で柔らかな色合いを、夏は涼やかな透け感と藍色や水色で清涼感を、秋は紅葉や菊などの温かみある色彩で落ち着きを、冬は松竹梅や椿などの格式高い柄で凛とした美しさを表現します。さらに、袷・単衣・薄物といった季節に応じた仕立てを選ぶことで、見た目だけでなく快適さも両立可能です。帯や長襦袢、小物も季節に合わせてコーディネートすることで、より洗練された印象になります。四季折々の自然をまとい、日本ならではの美意識を感じられる着物の世界を、季節ごとの装いでぜひ楽しんでみてください。